【カラデシュ】第6回 天才発明家ラシュミと盟友サヒーリ【ストーリー】
はじめに
前回までで、チャンドラが母と「安堵の再会」を果たすまでのお話をご紹介しました。
さて、今回の黒幕のテゼレットは、改革派の長ピアに憎しみを向けながらも、それとは全く別の目的で動いています。
今回はその「目的」につながる、とある"大発明"のお話…。
発明家の死闘
カラデシュにて発明展覧会が始まったその頃。
その大会で栄光を勝ち取ることを目指し、実験を続ける霊気技術者がいました。
彼女ーラシュミと、その助手のヴィダルケンーミタルは、ちょうど848号目の被験体に着手したところなのでした。
「準備はいい?」 彼女は尋ねた。
ミタルは頷いた。彼は霊気測定装置が並ぶ背の高い机の隣に立ち、筆記具は実験日誌に構えられていた。
「準備できました」
あなたならできる、ラシュミは密かに被験体第848号を励ました。
「了解です。転送器を離します。3……2……1……」
彼女がその輪を手離すとただちにその内の霊気がうねり、輪は花の真上の空中に浮かび上がった。
「計測開始」 ミタルが実験日誌へと記入した。「開始時の霊気量を記録」
霊気を穏やかに発散しながら、輪は下降を開始して花弁へと向かっていった。
(中略)
輪が花弁の高さにまで降りてきた時、ミタルの声は遥か遠くからのように聞こえた。
「接触時間を記録」
ラシュミは息をのんだ。
輪が通過すると、花弁の先端が震えた。金色の転送器は下降を続けた。
また震えた。
そして突然、花そのものの構造が屈し、小さな爆発音とともに花全体が内破して輪郭が塵と化した。
(中略)
「実験失敗。被験体第848号は消滅」 ミタルが告げた。
ラシュミは溜息をつき、転送器の金属に指を滑らせて破損具合を見積もった。
今度こそは成功する、心からそう考えていた。
ラシュミが作っていたのは、物質の転送装置。
完成すれば、発明展覧会での優勝は確実。
そしてそれは、この世界の法則すらも変えられることを意味するもの。
彼女はそれを開発し、今まで800回以上もの被験体で実験を繰り返していたのでした。
しかし、発明展覧会への提出期限が一週間を切っている今、いまだに成功しない実験に二人は焦りを感じていたのです。
そして、それからあっという間に一週間は経ち。
発明展覧会への提出期限が午後に迫る日。
彼女ら二人は、二日間も不眠不休の中、期限に間に合う最後の実験に着手したのでした。
「計測開始、霊気量を記録」 ミタルが日誌に印をつけ、赤くなった目をこすった。
ラシュミは客観的な観測者という自身の立場を保とうと努めたが、うなだれた花弁へと輪が下降していく中、気がつくと彼女はまたも息を止めて祈っていた。今回こそ上手くいく、意地でも成功させなければ。
輪が花弁の最上部を通過した。「接触時間を記録」 ミタルの声。
花弁が揺らめいた。弾けないで。弾けないで。ラシュミは心から願った。
(中略)
花全体が瞬き、現れては消え、ラシュミの全身の筋肉が緊張し、そして――
ポン! 花が内破した。
ラシュミの内が凍り付いた。そんな。輪は音と火花を上げていた。そんな。フィラメントが屈して切れる音がした。そんな! こんなことが起こるはずがなかった。ありえなかった。
「試験失敗。被験体第887号は消滅」
ラシュミの中で、全てが崩れ去る音がしました。
終わった。
自分は何のために、全ての時間を費やしてこの発明に着手したのか。
この実験の失敗は、自分がこの後発明家としても長くはやっていけないことを意味しています。
常に自分のそばで支えてくれたミタルにも、合わせる顔がない。
「ラシュミ」 その声に何かを感じ、彼女は振り返った。
「み、見て下さい」 彼はしきりに瞬きをしながら、研究室の隅を指差していた。
ラシュミは彼の指先を辿った。そこに、小さく記された輪の中、壁にもたれかかって、花瓶があった。
ラシュミの息が止まった。
振り返って部屋の中央の机を見ると、そこには輪だけがあった。目の錯覚、違う花瓶、最初はそう思った。だが見間違えようもなかった。
(中略)
ラシュミは笑い声を上げた。不意に上がってきたのは奇妙に響く笑い声だった。笑い続けなければ心臓が喉から飛び出て窒息してしまいそうだった。一言を発することすら困難だった。
「ミタル……ミタ……わ、私達……」
「はい」 ミタルは今も激しく瞬きをしていた。
「非有機体を空間を越えて転送することに成功しました」
「ああ! やった!!」
ラシュミの目の奥に熱と湿気が沸き上がり、彼女は友へと駆け寄ってその両腕を長身のヴィダルケンの首に回して強く抱きしめた。
「私達、本当にやったのよ」
歓喜に沸く二人。
がすぐに我に返ります。
発明博覧会への提出期限。
今からなら、なんとか期限に間に合う。
そのために、転送装置に新しいフィラメントを取りつけ、機械を輸送する必要がありました。
しかし、フィラメントを取りに行ったミタルは、青白い顔をして帰ってきたのです。
予備のフィラメントはもうないのだと。
彼の十二本の指がその長く青い顔の周囲で震えた。
「大丈夫ですよ、ミタル」
ラシュミは彼の肩に手を置いた。奇妙に落ち着いていた。大導路からの導きを感じ、そしてやるべき事を知っていた。
「装置を梱包して下さい。それを市場まで運んで、そこでフィラメントを手に入れてから博覧会へ向かいましょう。それでも提出期限までには闘技場へ行けるはずです」
「あっ」 ミタルは瞬きをした。
「あ、そうですね」 彼は長い溜息をついた。「それで大丈夫だと良いのですが」
「大丈夫でしょう。今は私達の時ですから」
魔法的金属技師サヒーリ
結論から言うと、フィラメントはどこにもありませんでした。
発明展覧会を控え、誰もが予備や代用品を欲する中、市場のどこにもフィラメントはなくなっていたのでした。
大きな疲労感とともに、橋の欄干によりかかるラシュミ。
自責の念に押しつぶされそうなミタルに、彼女は告げます。
もう自分たちの実験のための調査球は閉じるしかないと。
しかし、そこで突然かけられた声に、ラシュミは橋から落っこちそうになります。
「生きてたのね!」
それは自分を探していたという、友人サヒーリの声。
「ひどい有様じゃない。何をしていたの? 闘技場で名前を呼ばれていたけれど」
ラシュミの両目に涙が溢れ出た。それを止める力はなかった。
「どうしたの?」サヒーリは横にやって来て、片手でラシュミの肩を抱きしめた。「何があったの?」
ラシュミはかぶりを振った。
「終わったの。フィラメントが切れて、それだけ。替えはどこにもないの。街のどこにも」 涙の粒が落ちた。
「ああ、よしよし」 サヒーリはラシュミの背中を撫でた。
「大丈夫。傷ついた金属片があるなら、私を呼ぶことは思いつかなかったの?」
ラシュミは鼻をすすった。「あなた?」
そして気が付いた。
「あなた! あなたなら直せる」
希望の光が見えたラシュミは、まくしたてるように話し始めます。
自分が当初作り出していた、霊気凝縮装置の話。
そして、それを組み込んだ転送装置の話。
それがどれほどまでに革新的なことか。
それを完成させてくれる友へ、どれほど感謝しても足りないか。
そんなの言葉とともに、ラシュミは切れたフィラメントを、サヒーリに差し出したのでした。
だがサヒーリはそのフィラメントを受け取らなかった。身動きもしなかった。
「どうしたの?」
サヒーリはうつむいて一歩引き下がった。
「ごめんなさい。私はそれを直したくない。友達のあなたを傷つけたくはないけれど、できない」
「できないって何を?」ラシュミは混乱していた。
(中略)
「あなたは何も知らないのよ。それがどうやって動いているのかすらも。あなたの設計が起こす可能性のある結果も。それは危険すぎる」
ラシュミはサヒーリの言葉を全く把握できなかった。
「私はもう行かないと」彼女は階段を降りた。
ラシュミの怒りが頂点に達した。
「だったら何? 自分が作り出した革新だけを信じてるってこと? 自分だけが注目されたがってるの?」
サヒーリの首筋が強張った。
「サヒーリ、あなたは栄光の中で生きてきた。今度は私の番。それは嫉妬? 博覧会で一番輝くのはあなたの発明じゃない、それを心配してるの?」
サヒーリの手が拳に握られ、だが彼女は振り返りも足を緩めもしなかった。ラシュミは友人と思っていた女性が、最も必要とする時に自分の前から去ってゆくのを見つめていた。
サヒーリの決断
高名な発明家であり「プレインズウォーカーである」サヒーリは、ラシュミの発明の危険性がわかりました。
それは、"世界に穴をあける"発明だと。
憂さ晴らしのように、改革派の自動機械決闘を続けるなか、彼女の中でぐるぐると思考が廻ります。
ラシュミの助力を退けたのは、彼女に指摘された「嫉妬」などでは全くない。
これは、彼女と、ひいてはこのカラデシュを守るために正しいことであったと。
“外の世界"を知らないラシュミには、自分の言説は理解できないだろう…と。
気晴らしになると思った決闘によって、自分の怒りは増すばかりでした。
そんな闘技場から去ろうとする中、唐突に彼女に話しかける影があったのです。
それは、自分に憧れ、自分の写る小冊子とともに、サインをねだるドワーフの娘。
彼女からペンを受け取ったサヒーリは、冊子に記された自分の発現に目を奪われます。
規制と規則に縛られる時代もありますが、この革新の時代はそうではありません。怖れることなく突き進みましょう。束縛されることなく創造しましょう。手をとり合って力の限りに驚くべきものを創造し、並外れたことを達成し、世界を変えるのは発明家としての義務です。
気づけば、サヒーリは走り出していました。
失いかけている友のもとへ。
そして、夢中で走ってきた彼女には、調査球の扉を叩いたその時まで、自分が何をすべきか、何を言うべきかもわからなかったのでした。
ただ、すべてが手遅れになる前に、何かをしなくてはいけないという思いだけ。
扉を開けてくれた友の、絶望にまみれた凄絶な姿を見て、サヒーリは口を開いたのでした。
「どうして力になれなかったのか、説明しないといけないと思って」 ラシュミは目を合わそうとしなかった。
「怖いし、自信がなかったの。あなたのしている事は危険で――」
「それはもう聞いたわ、サヒーリ」 ラシュミは背筋を伸ばした。
「もしまた私に講義しに来ただけなら、出ていって」
ラシュミは扉を閉めようとしたが、サヒーリは素早くそれを止めた。
「最後まで言わせてよ」 サヒーリは扉と枠の間に割って入った。
「そう、危険。でも」 ラシュミが目玉を動かす音が聞こえるようだった。彼女は続けた。
「すごくわくわくする。ぞっとするくらい。世界を変えられるかもしれない――良いことのために」
ラシュミは扉から手を放さないまま、僅かに背筋を伸ばした。
「あなたなら霊気学で次の革新を起こせる。私も一緒にそれを見たい。力になりたいの」
サヒーリは完璧に形成されたフィラメントを取り出した。それは彼女が呼び起こせる最も頑健な金属から織り上げたものだった。
「これをあなたに」 彼女は続けた。「パディームも言ってたわ、もしそれが動くなら見たいって」
ラシュミは彼女を見つめ、そしてその両目はゆっくりとフィラメントへと移動した。
無言で受け取ったラシュミは、そのまま実験台へと移動します。
そして、転送機を作動させ、一瞬のうちに、実験台の上の花を部屋の隅へと移動させたのでした。
サヒーリは見つめ、驚きに開いた口が塞がらなかった。友人は不可能をやってのけた。その装置は今や空間を越えて物体を運んでいた。
自分は正しいことをした、サヒーリはそう願うだけだった。
やがて二人が訪れたのは、発明展覧会の審判者パディームのもと。
提出期限はとっくに過ぎていましたが、サヒーリが「地下工匠対決の最前列の席」という名の”賄賂”を渡すことで、ラシュミの発明の評価の機会を得たのでした。
審判者ともあろうヴィダルケンが決闘を行う、という知られざる事実に混乱するラシュミを、サヒーリは会場へと招きます。
「ありがとう」 ラシュミはサヒーリへと深く頭を下げた。
「ありがとう。何もかもあなたのおかげ。終わりのない感謝を」
サヒーリは肩をすくめた。
「もっと上手く言えたかもしれないのにね。ごめ……ごめんなさい」 彼女はラシュミを睫毛越しに一瞥した。
「まだ友達でいてくれる?」
「ずっと」 ラシュミはサヒーリを抱きしめて引き寄せた。
サヒーリは彼女の腕を握りしめた。
「さあ、世界を変えるかもしれない発明をあの決闘ヴィダルケンに見せてきなさい」
(中略)
「領事、発明家ラシュミ氏とミタル氏をお連れしました」 職員が言った。
パディームは頷いた。「ようこそ」
(中略)
パディームは指先に顎を乗せて言った。
「宜しいでしょう。発明家ラシュミ、私を驚かせなさい」

今回はここまで
刷られたカードも強かったため、カラデシュ=チャンドラの物語、と思われる方も多いかもしれません。
が!影の主人公…というか第二の主人公は、このラシュミの物語です。
彼女の、自分の世紀の発明をめぐる努力、希望、絶望、苦悶、そして栄光の物語は、読んでいるこちらも手に汗握るものになっています。
この素晴らしさが少しでもご紹介できていれば嬉しいですね。
というか、この記事であらすじをわかったら、ぜひ下のリンクから元記事も読んで!!
さて、結果としてはサヒーリの予感が正しく、ラシュミのこの発見は後の多元宇宙を巻き込む大事件の一助となってしまうわけですが…それはまた少しあとのお話。
次回は、栄光をつかんだラシュミと、彼女を利用せんとする悪党テゼレットのお話をば。
お楽しみに!
☆Twitterで更新情報発信中!フォローお願いします!
Follow @okhrden_mtg
【関連記事】
*出典*




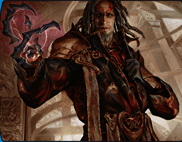

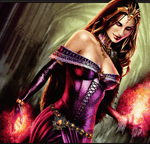





Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!